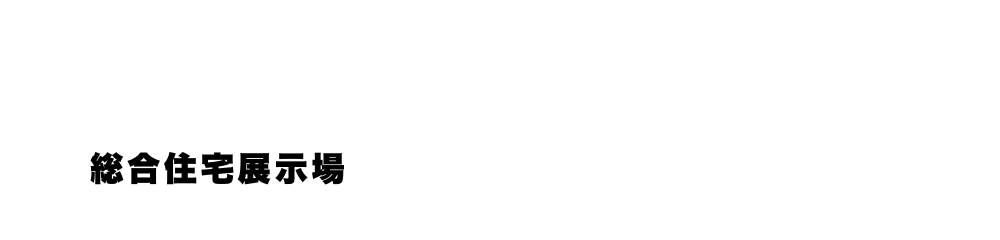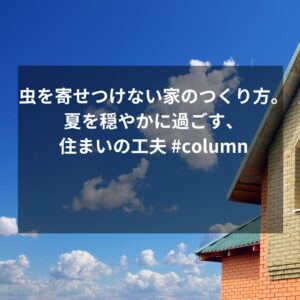未来の備えは「今の選択」から。相続対策にもなる賢いリフォーム術 #column
「相続なんて、まだまだ先の話」──そう考えている方も、親の住まいや土地のことがふと頭をよぎる瞬間、ありませんか?突然の相続発生は、金銭面や手続き面で思わぬ混乱を招きがちです。
そんななか注目されているのが、“相続前のリフォーム”。実はこの一手が、暮らしやすさの向上だけでなく「節税」につながる可能性があるのをご存じでしょうか?
この記事では、相続税の仕組みや不動産評価の考え方、そしてリフォームとの関係を解説します。家族の未来を見据えた準備として、知っておきたい情報を整理しました。
この記事を読めばわかること
- 相続税の仕組みと不動産の評価方法
- リフォームが相続税に与える影響
- 節税につながるリフォームと注意点
- 相続前にやっておきたい手続きや相談先
1. 相続税の基本──不動産の比重に要注意
相続税は、亡くなった方の「遺産総額」から基礎控除額を差し引いたうえで、その残額に対して課税されます。
【基礎控除の計算式】 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
この控除額を超えた場合にのみ、相続税が発生する仕組みです。
ここで問題になるのが「不動産の評価の難しさ」。特に築年数が古い住宅や土地付きの家は、実際の価値と税務上の評価にズレが生じやすく、相続時のトラブルの原因になることも少なくありません。
2. 建物評価額はどう決まる?──市場価格とは別のロジック
相続税の対象となる不動産評価額は、市場での売買価格ではなく、「固定資産税評価額」をベースに算出されます。
評価額の基本ポイント:
- 築年数が経つほど、減価償却により評価額は下がる
- 木造よりも鉄筋コンクリート造(RC造)の方が耐用年数が長く、評価が高くなる傾向
つまり、「古い家なのに税金が高いのでは?」という心配は原則不要ですが、リフォームによって評価額が上がる場合がある点は注意が必要です。
3. リフォームで評価額が上がる?──節税になるかの見極めポイント
ここからが本題です。リフォームによって評価額がどう変わるかは、「その内容」によって大きく異なります。
節税効果が期待できるリフォーム(評価額が基本的に変わらない)
- キッチンや浴室の老朽化設備の交換
- 外壁や屋根の塗装・防水工事
- バリアフリー化や断熱改修など、省エネ性や安全性向上のための工事
これらは、「建物の価値を元に戻す」工事と見なされるため、原則として固定資産評価額に大きな影響はありません。
節税効果が薄い/評価額が上がる可能性のあるリフォーム
- 増築(建物面積の拡大)
- 高級素材や意匠性の高いリノベーション
- 太陽光発電設備や蓄電池の新設など、新たな機能を付加する工事
これらは「資産価値の向上」と判断される可能性があるため、評価額アップ→相続税増のリスクがあります。
したがって、「相続前にリフォームすれば節税できる」と一概には言えず、どんな工事を、どの目的で行うかが鍵になります。

4. リフォーム費用で相続財産が減る?──支出と評価のバランス
現金資産を使ってリフォームを行うことで、相続時の「財産の総額」が減少し、結果として課税対象額も減るという考え方もあります。
たとえば、以下のようなパターンが想定されます。
- 預金から工事費を支出 → 現金残高が減る
- 一方で、リフォーム内容が「価値回復工事」であれば、家屋の評価額はほぼ変わらない
このように、全体の相続財産をコントロールする手段としてリフォームが使えることがあります。ただし、節税の意図が過剰だったり、内容や金額が不自然な場合は、税務署から否認されることもあります。
慎重な判断と専門家の助言が不可欠です。
5. 贈与と見なされないための注意点──“誰が払ったか”がカギ
リフォームにおいて意外と見落とされがちなのが、「費用の出どころによる贈与認定リスク」です。
たとえば:
- 親名義の家を、子どもが自分の資金でリフォーム → 親への贈与と判断される可能性
- 年間110万円を超える支出は、贈与税の申告対象になることも
また、親が「子の将来のため」としてリフォーム費を負担した場合でも、その内容によっては子への贈与と見なされることがあります。
相続と贈与の境界線は非常に曖昧であるため、事前に税理士などの専門家に確認しておくことをおすすめします。
6. 相続前に進めておきたい3つの準備
「相続が起きてから」ではなく、「起きる前」に備えておくことが、安心と節税の両立につながります。
【ステップ1】現状の確認
- 建物の築年数や構造を把握
- 固定資産税評価証明書を取得し、評価額を確認
【ステップ2】目的の明確化
- 住環境の改善か?節税対策か?
- どんな工事が本当に必要かを見極める
【ステップ3】専門家への相談
- 税理士や不動産鑑定士、ファイナンシャルプランナー(FP)など、信頼できる相談先を持つ
- 補助金制度や税制優遇措置の利用可否も併せて確認
まとめ
相続前のリフォームは、住まいの快適性向上だけでなく、相続税の節税にもつながる可能性があります。しかし、リフォームの内容や支払い方法によっては、思わぬ課税リスクを招くこともあるため、慎重な対応が求められます。
まずは家族でじっくり話し合い、必要に応じて専門家と一緒に計画を立てていきましょう。リフォームを通じて「住まいの価値を整える」ことが、次世代への安心につながります。
住宅展示場などでは、リフォームや相続対策に関する相談窓口を設けているところもあります。気軽に足を運び、今できる一歩から始めてみませんか?