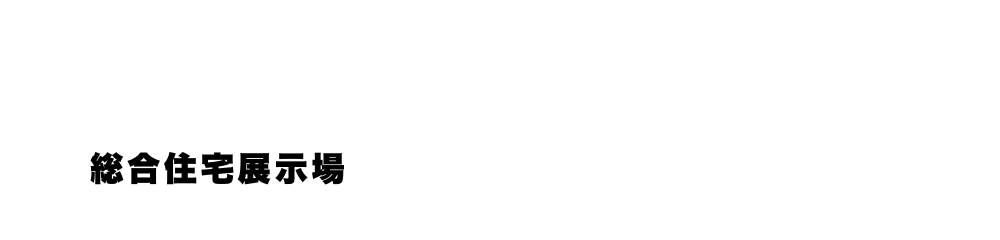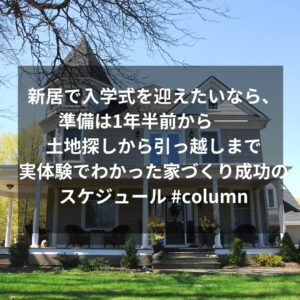料理の流れが止まらない! —— キッチン収納を変えるだけで“探すイライラ”が消える理由 #column
この記事を読めば分かること
- どうしてキッチンは散らかりやすいのか
- 収納を考えるときの“行動動線”という新しい視点
- 4つの収納エリアごとの実践テクニック
- よくある失敗例とその解決策
- 今日からすぐできる収納改善のステップ
はじめに
想像してください。
カレーを作ろうとしたあなたは、まず玉ねぎを切り、次に鍋を取ろうとシンク下を開ける。けれど、鍋が重なって取り出しにくい。やっとの思いで鍋を出すと、今度はルウの箱が見つからない——そんな小さなつまずきが、料理全体のリズムを狂わせていませんか?
料理の効率を決めるのは、実は「レシピ」よりも「収納」。
この記事では、単なる片づけのコツではなく、「動線」と「習慣」に寄り添ったオリジナルの収納術をお届けします。
キッチン収納の考え方:モノではなく“行動”から逆算する
行動が収納を決める
料理は「準備 → 加熱 → 盛りつけ → 後片づけ」という流れがあります。
収納を考えるときは、この行動の順番に合わせてモノの置き場所を決めると、自然と使いやすくなります。
例:
- 野菜を切る前に使う「ボウルやザル」はシンクの近くへ
- 加熱時に使う「鍋・フライパン」はコンロ下へ
- 盛りつけで使う「器・保存容器」は調理台下へ
“動線の近さ”が時間を生む
モノの種類ではなく「どの動作で使うか」で分ける。これが、散らからないキッチンの秘密です。

4つのゾーン別オリジナル収納術
1. シンク下 — 「水まわりゾーン」
ここは“水と戦う場所”。
排水管があり湿気が多いため、食品はNG。
代わりに、洗剤や掃除用具、調理前に使うザル・ボウルを配置します。
👉 ポイント:ラックを使い上下を分け、「洗う道具」と「調理準備の道具」をエリアごとに区切る。
2. コンロ下 — 「加熱ゾーン」
鍋・フライパン・油など、火を使うときの必需品を集めます。
重ねずに立てることで、取り出す動作を一瞬に短縮。
👉 ポイント:仕切りを使って「鍋の種類ごと」に独立させる。取っ手が見える状態にしておけば、迷うことなく使える。
3. 調理台下 — 「仕上げゾーン」
ここは料理のラストスパートで活躍する場所。
保存容器、ラップ、よく使う調味料、キッチンツールを集結。
👉 ポイント:透明容器+ラベルで“見える収納”。開けた瞬間に目的のものが目に入る仕組みにする。
4. 吊戸棚 — 「ストック&シーズンゾーン」
手が届きにくいため、軽くて出番が少ないものを収納。
乾物やお菓子のストック、季節限定の食器を置くのに適しています。
👉 ポイント:取っ手付きケースを活用し「箱ごと下ろす」スタイルにすれば、高さ問題を解消。
よくあるNG収納パターンと解決策
- NG1:鍋を積み重ねる
→ 改善:フライパンラックやブックエンドで立てる収納に。 - NG2:吊戸棚に重い調理家電を入れる
→ 改善:下段か床収納に移動。安全第一。 - NG3:収納グッズがバラバラで中身が分かりにくい
→ 改善:透明ケースや統一デザインの容器に変更。ラベル必須。
今日から始められる3ステップ
- 全部出す:まずは現状をリセット
- 動線で分ける:「使う場所の近く」に分類
- 仮置きして試す:1週間試して合わなければ調整
収納は“一度決めたら終わり”ではなく、“暮らしに合わせて変える”もの。
情景描写でイメージする「理想のキッチン」
夜、あなたが調理台に立つ。
包丁で玉ねぎを切りながら、シンク下からボウルを片手で取り出す。
コンロ下を開けるとフライパンが縦に並び、迷うことなく選べる。
仕上げに調理台下を開けると、保存容器が整然と並び、ラベルで中身が一目瞭然。
吊戸棚には、使わない季節物がケースごと収まっていて、邪魔をしない。
その流れは途切れず、料理が“心地よいリズム”になる。
まとめ
キッチン収納の本質は「モノの種類」ではなく「行動動線」。
シンク下・コンロ下・調理台下・吊戸棚をそれぞれの役割に沿って整えるだけで、あなたの料理時間は驚くほど快適になります。
今日から始められるのは「全部出して、動線で分けて、仮置きする」。
小さな一歩が、あなたの毎日の料理をストレスフリーに変えます。