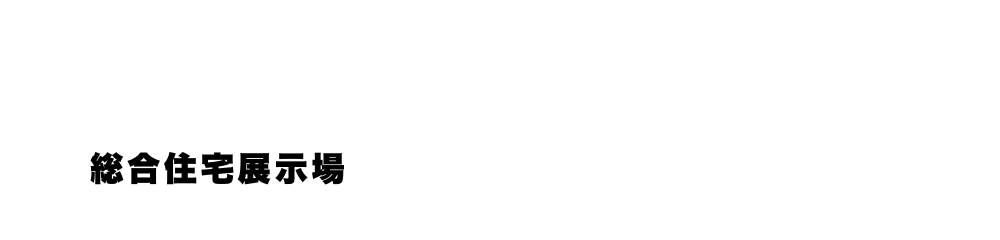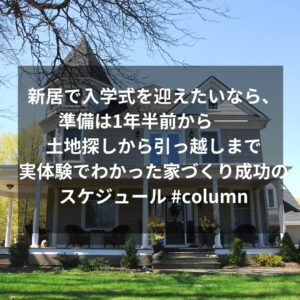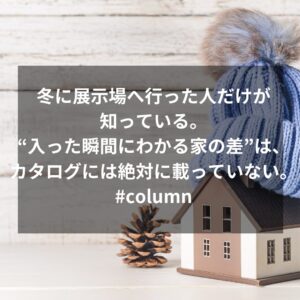飾る収納は“舞台”、隠す収納は“楽屋” —— 二つを分けるだけで、部屋はモデルルームのように洗練される #column
この記事を読めば分かること
- 見せる収納と隠す収納を使い分けるメリット
- 生活感を隠しながらおしゃれに見せる工夫
- 見せる収納に適したアイテムと隠すべきアイテムの具体例
- 実践するときの注意点と失敗回避のポイント
- 今日から取り入れられる“メリハリ収納のはじめ方”
はじめに
人を招いたとき、部屋を見渡してこう感じたことはありませんか?
「片づけたはずなのに、なんだか雑然として見える」
その理由は単純です。全部を見せているか、全部を隠しているかのどちらかに偏っているから。
収納は、「舞台」と「楽屋」を意識して分けることでガラリと変わります。
舞台(見せる収納)は、あなたのセンスを表現する場所。
楽屋(隠す収納)は、生活感をすべて引き受ける裏方。
この記事では、その二つをどう使い分ければ、部屋全体の印象が一段と洗練されるのかを解説します。
見せる収納は“部屋の表情”をつくる
◆ 見せる収納の役割
見せる収納は、部屋の雰囲気やあなたのライフスタイルを演出する舞台です。
観葉植物、アートブック、デザイン性のある食器……。置くだけで空間の質感が引き上がります。
◆ 向いているアイテム
- デザイン性がある日用品(おしゃれなティッシュケース、ガラス瓶の調味料など)
- 季節感を出せる小物(花、キャンドル、アート作品)
- 愛着があるコレクション(カップ、フィギュア、写真)
◆ 美しく見せる3つの工夫
- 色や素材をそろえる:色数を抑えると統一感が出る
- 空白を残す:飾る量は7割、残り3割は余白でバランスを取る
- 高さにリズムをつける:同じ高さで並べないことで動きが生まれる
隠す収納は“暮らしを守る裏方”
◆ 隠す収納の役割
隠す収納は、舞台裏を支える楽屋のようなもの。
コード、リモコン、書類、買い置きのお菓子や日用品……これらが視界に入ると一気に生活感が強くなります。
◆ 隠した方がよいアイテム
- 不揃いな形や派手な色のパッケージ類
- 日常的に使うが“おしゃれではない”アイテム(掃除道具、調味料の袋)
- 散らばりやすい小物(文房具、郵便物、レシート)
◆ 使いやすい隠す収納の工夫
- ケースや仕切りで定位置をつくる
- 半透明のボックスで中身を見える化
- 扉裏にポケットやフックを取り付けて“隙間収納”
実際の暮らしに取り入れるステップ
- 部屋にあるモノを全部「見せたい」「隠したい」で分ける
- 見せるモノは量を絞り、インテリアとして“飾る意識”で配置する
- 隠すモノはケースや引き出しにまとめ、誰でも片づけられる仕組みにする
- 1週間暮らしてみて「使いづらい」と感じたら場所を調整する
よくある失敗と改善例
- 見せる収納に詰め込みすぎる
→ 出す量を減らし、余白を残すことで洗練される - 隠す収納の中がごちゃごちゃ
→ 仕切りやラベルを活用して“戻しやすさ”を最優先に - 家族が収納ルールを知らない
→ ラベルで「誰でも分かる」状態をつくる

情景でイメージする“理想の空間”
休日の昼下がり、友人を招いたあなた。
部屋にはお気に入りの本と観葉植物が棚に並び、心地よい音楽が流れている。
一方で、生活感の強いリモコンや書類はキャビネットの中に整然と収まっている。
友人が「すごく落ち着く部屋だね」と言うと、あなたは少し誇らしい気持ちになる。
これが「見せる収納と隠す収納のメリハリ」がもたらす効果です。
まとめ
収納はただの片づけではなく、暮らしをデザインする行為です。
- 見せる収納は舞台:センスや季節感を表現する場所
- 隠す収納は楽屋:生活感を引き受け、暮らしを支える場所
この二つを意識して分けるだけで、部屋の印象は劇的に変わります。
あなたも今日から「メリハリ収納」を取り入れて、洗練された暮らしを始めてみませんか?