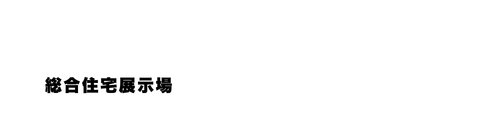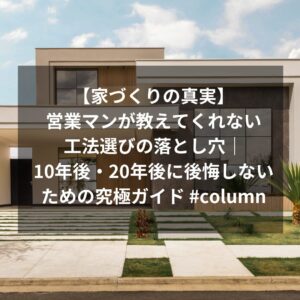「コンセント? 適当でいいや」が引き起こした3年間の後悔と、今だから語れる新築電源設計の真実#column
この記事を読めば分かること
この記事では、新築住宅の電源設計について、以下のことが具体的に理解できます。
- なぜ多くの人がコンセント配置で後悔するのか、その心理的メカニズム
- 「充電する生活」を前提にした現代型コンセント設計の考え方
- 各部屋の用途別に見る「これだけは外せない」電源ポイント
- 家族構成とライフステージ変化に対応する柔軟な電源計画
- 美しさと機能性を両立させるコンセント配置の美学
- 建築コストと将来の利便性のバランスを取る判断基準
はじめに
新築の打ち合わせ4回目。テーブルの上には、間取り図、設備のカタログ、サンプルのタイルや壁紙が山積みになっていました。
「次は電気配線とコンセントの位置を決めていきましょう」
設計士さんの言葉に、私は正直、少し面倒だなと思いました。リビングの広さをあと30センチ広げたい。キッチンのタイルの色をもう一度確認したい。そっちの方がずっと重要に思えたんです。
「コンセント? まあ、普通に付けておいてもらえれば大丈夫です」
そう答えた私に、設計士さんは少し心配そうな表情を浮かべました。
「本当に大丈夫ですか?入居後、一番後悔するのがコンセントの位置と数なんですよ」
その言葉の意味を、私が本当に理解したのは、新居に住み始めてから半年後のことでした。
洗面所で髪を乾かそうとドライヤーを手に取ったとき、電動歯ブラシの充電器を抜かなければならないことに気づきました。毎朝、この小さな作業が必要になる。365日、10年で3,650回。この繰り返しが、じわじわとストレスになっていくんです。
リビングのソファでくつろぎながらスマホを充電したいのに、コンセントは3メートル先。充電ケーブルを床に這わせるか、諦めるか。どちらを選んでも、理想の暮らしからは遠ざかります。
キッチンで新しく買った電気圧力鍋を使おうとしたら、コンセントが足りない。延長コードを引っ張り出すと、コード類が絡まって、せっかくのモダンなキッチンが台無しに。
「あのとき、もっと真剣に考えていれば…」
そんな後悔を、何度したかわかりません。
でも、すべてが失敗だったわけではありません。設計士さんのアドバイスを素直に受け入れた部分もあり、そこは毎日「本当にここに付けて良かった」と感謝しています。
この記事では、3年間の実生活から学んだ「コンセント配置の成功と失敗」を、包み隠さずお伝えします。私の失敗が、あなたの成功のヒントになれば幸いです。
なぜ人はコンセント計画を軽視してしまうのか
友人5人に、家づくりで後悔していることを聞いてみました。すると、全員が「コンセント」を挙げたんです。
でも不思議なことに、5人全員が「打ち合わせのときは、あまり重要だと思っていなかった」とも答えました。
見えない敵は軽視される
人間の脳は、目に見えるものを優先して判断します。
壁紙の色、床材の質感、キッチンのデザイン、お風呂の広さ。これらは写真やサンプルで確認でき、完成後のイメージが湧きやすい。だから真剣に考えられます。
でも、コンセント?
「白い四角いアレでしょ」くらいの認識。どこに付けても同じように見える。だから、「まあ、普通に付けておけば大丈夫だろう」と思ってしまうんです。
生活の「動詞」が欠けている
もう一つの理由は、家づくりの打ち合わせが「名詞」中心だということ。
「リビングを広く」「キッチンを対面式に」「寝室を南向きに」。これらは全て「もの」や「状態」の話。
でも、実際の生活は「動詞」で成り立っています。
「充電する」「乾かす」「温める」「照らす」「調理する」「掃除する」。これらの行動には、すべて電源が必要です。
名詞だけで家を設計すると、動詞が抜け落ちる。結果として、「見た目はいいのに使いにくい家」が出来上がってしまうんです。
現代生活は「電力依存型」
もう一つ、見落とされがちな事実があります。
現代の生活は、10年前、20年前とは比較にならないほど「電力依存」になっているということ。
スマートフォンが普及したのは、わずか15年前。ワイヤレスイヤホンが一般化したのは、ここ5〜6年。電動歯ブラシ、スマートウォッチ、タブレット、モバイルバッテリー…。
充電が必要な機器は、加速度的に増え続けています。
でも、私たちの「家のイメージ」は、無意識に「昔の家」をベースにしている。だから、必要なコンセントの数を大幅に見誤ってしまうんです。

「電化製品の履歴書」を作る重要性
住み始めて1年が経ったころ、私はあることに気づきました。
新しい家電が、次々と増えているんです。
引っ越し前には持っていなかったもの:コーヒーメーカー、ホームベーカリー、電気圧力鍋、ロボット掃除機、加湿器2台、空気清浄機、スマートスピーカー3台、ワイヤレス充電器…。
「なぜこんなに増えたの?」と夫に聞くと、「新しい家だから、新しい家電が欲しくなるんだよ」と笑っていました。
家電は「増える生き物」として扱う
家を建てるとき、多くの人が犯す間違いがあります。それは「今持っている家電」だけを基準にコンセントを計画すること。
でも、家電は増えます。確実に。
理由は3つ。
理由1:新生活への期待
新しい家に住むと、生活スタイルを変えたくなります。「パンを焼いてみようか」「コーヒーにこだわってみようか」。その度に、新しい家電が増えます。
理由2:技術の進化
毎年、新しい便利家電が登場します。「これ、便利そう」と思ったとき、コンセントがないと使えません。
理由3:ライフステージの変化
子どもが生まれれば、哺乳瓶の消毒器や電動鼻水吸引器。子どもが成長すれば、学習用タブレットやゲーム機。親が年を取れば、電動ベッドや健康管理機器。
家族の変化は、家電の変化でもあるんです。
5年後の自分にインタビューする
私がおすすめする方法があります。それは「5年後の自分を想像して、インタビューする」こと。
5年後のあなたは、どんな生活をしていますか?
子どもは何歳になっていますか?その年齢の子どもは、どんな電化製品を使いますか?
趣味は変わっていますか?新しく始めたい趣味に必要な機器はありますか?
在宅ワークをしていますか?週に何日、家で仕事をしますか?
こうして想像すると、今は必要なくても、将来必要になるコンセントが見えてきます。
ゾーニング思考で整理する
電化製品をただリストアップするだけでは、まだ不十分。それらを「場所」と「用途」で整理する必要があります。
私が実践した方法を紹介します。
ステップ1:場所で分類
玄関エリア、リビングエリア、ダイニングエリア、キッチンエリア、洗面所エリア、寝室エリア、子ども部屋エリア、書斎エリア…。家を機能別のエリアに分けます。
ステップ2:用途で分類
各エリアで「何をするか」を動詞で書き出します。充電する、調理する、乾かす、読む、作業する、掃除する、くつろぐ…。
ステップ3:機器をマッピング
各動詞に必要な機器を紐付けます。「充電する」なら、スマホ、タブレット、イヤホン…という具合に。
ステップ4:優先順位を付ける
「毎日使う」「週に数回」「たまに使う」で分類。毎日使うものほど、アクセスしやすい位置にコンセントが必要です。
この作業、最初は面倒に感じるかもしれません。でも、一度やってしまえば、あとは設計士さんに渡すだけ。この「電化製品の履歴書」が、あなたの家のコンセント計画の設計図になります。
水回りは「時間との戦い」が起きる場所
朝7時15分。私は洗面所で戦争をしています。
娘の髪をドライヤーで乾かしながら、自分の電動歯ブラシは充電中。夫は電気シェーバーを使いたいけど、コンセントが足りない。「ちょっと待って!」「早くして!」。毎朝、この攻防戦が繰り広げられます。
朝の10分は夜の1時間に匹敵する
洗面所という空間には、特別な時間圧力があります。
朝、家族全員が集中する時間帯。出勤や登校の時間は決まっていて、遅れることは許されません。その限られた時間の中で、身支度を整えなければならない。
だから、「ちょっと待つ」という数十秒が、異常にストレスフルに感じるんです。
洗面所コンセントの黄金比率
私が住んで学んだ、洗面所のコンセント配置の法則があります。
法則1:家族人数+2口
家族が4人なら、最低6口。「同時に使う」ことを前提に設計します。
法則2:高さの二段構え
床から30センチの位置に2〜3口(常設充電器用)、床から100センチの位置に2〜3口(ドライヤーなど手に持って使う機器用)。
法則3:鏡裏の隠しコンセント
電動歯ブラシや電気シェーバーの充電器は、鏡の裏側に配置すると見た目がスッキリ。
我が家の失敗は、コンセントが床に近い位置に2口しかなかったこと。ドライヤーを使うたびに、充電器を抜いています。
洗濯機周りの見落とされがちなニーズ
洗面所でもう一つ重要なのが、洗濯機周辺。
洗濯機本体用のコンセントは当然ありますが、それ以外にも必要なものがあります。
- 衣類乾燥機(最近は室内干しが増えているため)
- 除湿機(洗濯物の部屋干し用)
- サーキュレーター(乾燥を早めるため)
- アイロン(洗濯機近くでアイロンをかける人も多い)
我が家では、洗濯機の横に2口のコンセントを追加で設置しました。これが大正解。梅雨の時期、除湿機とサーキュレーターを同時に使えて、部屋干しでも快適です。
キッチンは「層」で考える3Dコンセント設計
キッチンのコンセントを考えるとき、多くの人が「平面」で考えます。「この辺に3つ、あっちに2つ」という感じ。
でも、キッチンは立体的な空間。「層」で考える必要があるんです。
下層:床から30センチ(常設家電ゾーン)
ここには、毎日使う「動かさない家電」を配置します。
冷蔵庫、炊飯器、電気ケトル、トースター、電子レンジ、食洗機。これらは定位置があり、常にコンセントに挿しっぱなし。
我が家では、この層に8口のコンセントを配置。今、全て埋まっています。
中層:床から100〜120センチ(調理家電ゾーン)
ここは、調理中に使う「動かす家電」のゾーン。
ハンドブレンダー、フードプロセッサー、ミキサー、電動泡立て器。調理台の上で作業しながら、手を伸ばせば届く高さ。
この層のコンセントは、使わないときは目立たない位置に配置するのがポイント。我が家では、カップボードの側面に3口設置しました。
上層:床から150センチ以上(換気・照明ゾーン)
レンジフード、手元灯などの照明類。これらも電源が必要です。
このゾーンは設備工事の段階で配線されることが多いですが、後から「ここにペンダントライトを吊るしたい」と思ったときのため、天井にも配線を残しておくと良いでしょう。
収納内:パントリーの隠しコンセント
もう一つの「層」が、収納内です。
パントリーや食器棚の中にコンセントを設置すると、使わないときの家電を「隠し収納」できます。
ホームベーカリー、ヨーグルトメーカー、ミキサー。週末だけ使う家電を、パントリー内で充電・保管。使うときだけ取り出せば、キッチンカウンターは常にスッキリです。
我が家のパントリーには3口のコンセントがあり、これが本当に便利。「使いたいけど、出しっぱなしは嫌」という家電の居場所になっています。
見えないコンセントの美学
キッチンで私が最もこだわったのが、「コンセントを見せない工夫」。
標準的なコンセントは床から25センチの高さに付きます。でも、カップボードの上に炊飯器を置くと、コンセントが炊飯器の上に顔を出してしまう。
そこで、コンセントの位置をカップボードの天板から2センチ下げてもらいました。
すると、炊飯器の背面にコンセントが完全に隠れます。正面から見ても、コードが見えません。この「見えない2センチ」が、キッチンの印象を大きく変えました。
カップボード内部のコンセント配線
もう一つの工夫が、カップボードの引き出し内部にコンセントを設置したこと。
最上段の引き出しの奥に、2口のコンセント。ここに、タブレット用充電器とモバイルバッテリー充電器を常設。
キッチンで料理をしながらレシピをタブレットで見る。使い終わったら、引き出しに入れて充電。見た目はスッキリ、でも常に充電されている状態を保てます。
引き出しを閉めれば完全に見えないので、生活感ゼロ。この「隠す収納コンセント」、本当におすすめです。
リビングは「行動半径」でコンセントを配置する
リビングは家の中で最も長い時間を過ごす場所。だからこそ、コンセント配置の影響が大きいんです。
ソファからの「3メートル圏内」が勝負
人間の行動心理に、「3メートルの壁」というものがあります。
何かを取りに行くとき、3メートル以内なら「すぐ行く」と感じます。でも、3メートルを超えると「ちょっと面倒」という心理的抵抗が生まれるんです。
つまり、ソファでくつろいでいるときに使いたいもの(スマホ充電、タブレット、間接照明、ブランケットウォーマーなど)のコンセントは、ソファから3メートル以内に配置する必要があります。
ソファ周りの「黄金の三角形」
我が家のリビングで、最も成功したコンセント配置があります。それが「黄金の三角形」。
ポイント1:ソファの右側面(1メートル先の壁)
サイドテーブルの下に4口。スマホ充電、タブレット充電、読書灯、小型ヒーター用。
ポイント2:ソファの背面(50センチ先の壁)
床から60センチの高さに2口。間接照明用。ソファに座ったまま手が届く高さ。
ポイント3:テレビボード(2メートル先)
テレビ、レコーダー、ゲーム機、サウンドバー、Bluetoothスピーカー用に6口。
この3つのポイントが作る三角形が、リビングでの快適な生活を支えています。
子どもの「充電待ち喧嘩」を防ぐ工夫
子どもが2人いる我が家では、「充電の順番待ち」で喧嘩になることがありました。
「私のタブレット先に充電する!」「僕のゲーム機が先!」。コンセントの奪い合いです。
そこで、リビングのカウンター下に「子ども専用充電ステーション」を作りました。4口のコンセントに、それぞれの充電器を常設。自分の機器を、自分の場所で充電できるルールに。
これで喧嘩が激減。小さな工夫ですが、家族の平和に大きく貢献しています。
テレビ裏の「コード地獄」を回避する
リビングで最も配線が集中するのが、テレビ周り。
テレビ、レコーダー、ゲーム機、サウンドバー、Wi-Fiルーター、外付けハードディスク…。気づけば10本以上のコードが絡まり合う「コード地獄」に。
我が家では、テレビボードの背面に配線モールを設置し、すべてのコードを隠しました。さらに、コンセントは床から5センチの位置に6口を横一列に配置。
テレビボードで完全に隠れるので、正面から見てもコードは一切見えません。この「見えない配線設計」が、リビングの美しさを保つ秘訣です。
寝室は「就寝前30分」のために設計する
寝室のコンセント配置を考えるとき、多くの人が「寝るだけの部屋」と考えてしまいます。
でも、実際は違います。寝室は「就寝前30分のリラックスタイム」を過ごす場所なんです。
枕元のゴールデンゾーン
ベッドに横になったとき、手を伸ばせば届く範囲。それが「枕元のゴールデンゾーン」です。
この範囲内に必要なもの:
- スマホ充電器
- タブレット充電器
- スマートウォッチ充電器
- ベッドサイドランプ
- 間接照明
- 加湿器(冬)
- 小型扇風機(夏)
最低でも5〜6口のコンセントが必要です。
我が家の寝室は、ベッドの両サイドにそれぞれ4口ずつ配置。夫婦それぞれが、自分のデバイスを自分の側で充電できます。
「寝ながら充電」の高さを考える
ここで重要なのが、コンセントの高さ。
床から30センチの標準的な高さだと、ベッドに横になったとき、手を伸ばすのが大変。毎晩、体を起こしてコンセントに挿すのは面倒です。
おすすめは、床から60〜70センチの高さ。ベッドサイドテーブルと同じくらいの高さです。
ベッドに横になったまま、軽く手を伸ばせば届く。この「ちょうど良い高さ」が、就寝前の快適さを大きく変えます。
我が家では、ベッドの頭側の壁に、床から65センチの高さで4口のコンセントを設置しました。これが本当に便利。ベッドに入ってから「あ、充電してない」と気づいても、起き上がる必要がありません。
クローゼット内の「隠れた電源需要」
寝室でもう一つ、見落とされがちなのがクローゼット内のコンセント。
「クローゼットに電源?何に使うの?」と思うかもしれません。でも、実は用途がたくさんあるんです。
- 除湿機(湿気対策)
- 小型扇風機(換気用)
- Wi-Fiルーター(本体を隠したい場合)
- コードレス掃除機の充電スタンド
- アイロン(クローゼット内でアイロンがけする人も)
- 衣類スチーマー
我が家のウォークインクローゼットには2口のコンセント。除湿機を常設し、コードレス掃除機の充電スタンドも置いています。
クローゼットの扉を閉めれば見えないので、寝室の美観を損なわない。機能的で、見た目もスッキリ。一石二鳥の配置です。
子ども部屋は「5年サイクル」で変化する
子ども部屋のコンセント計画で最も難しいのが、「変化の予測」です。
小学1年生と高校1年生では、使う電化製品が全く違います。でも、コンセントは一度付けたら、簡単には変えられません。
年齢別電力需要マップ
実際の子育て経験から、年齢別の電力需要をマップにしてみました。
未就学児(0〜6歳)
- 電気スタンド(絵本を読む用)
- 加湿器
- 空気清浄機
- ベビーモニター(乳児期)
必要コンセント数:3〜4口
小学校低学年(7〜9歳)
- 上記に加えて
- 学習用デスクライト
- タブレット充電(学校配布)
- 目覚まし時計
必要コンセント数:4〜5口
小学校高学年(10〜12歳)
- 上記に加えて
- 自宅用タブレット
- 電子辞書
- 音楽プレーヤー
- ゲーム機
必要コンセント数:6〜8口
中学・高校生(13〜18歳)
- 上記に加えて
- スマートフォン
- ノートパソコン
- デスクトップパソコン(趣味による)
- 追加モニター
- スマートスピーカー
- 電気スタンド(学習用、高性能なもの)
- 小型冷蔵庫(受験期など)
必要コンセント数:8〜12口
この変化を見ると、「小学1年生だから4口あれば十分」と考えるのは危険だとわかります。
壁面分散配置の戦略
子ども部屋のコンセント配置で私が実践したのが、「壁面分散配置」。
一つの壁に集中させるのではなく、4つの壁にバランスよく分散させるんです。
北壁(窓側):3口 東壁(ドア側):2口 南壁(クローゼット側):2口 西壁(机を置く予定):5口
合計12口。
こうすることで、将来どんな家具配置にしても、近くにコンセントがある状態を保てます。模様替えの自由度も高まります。
娘が「机をこっちに移動したい」と言い出したとき、この分散配置が威力を発揮しました。どこに机を移動しても、近くにコンセントがあるので、問題なく対応できたんです。
兄弟姉妹の「コンセント争奪戦」対策
もし、一つの部屋を兄弟姉妹で共有する場合、コンセント計画はより慎重に。
それぞれのベッドエリア、それぞれの学習エリアに、独立したコンセント群が必要です。「共有」のコンセントだと、使う順番で喧嘩になります。
友人の家では、12畳の子ども部屋を将来的に仕切ることを想定し、両側の壁に均等にコンセントを配置していました。将来、壁を立てて6畳×2部屋にしても、それぞれの部屋に十分なコンセントがある状態。
この「将来の間仕切り」まで考えた設計、本当に賢いと思いました。
在宅ワークスペースは「集中力」のために配線を隠す
パンデミック以降、在宅ワークは「たまにやる」ものから「日常」に変わりました。
だからこそ、ワークスペースのコンセント設計は、単なる「口数」だけでなく、「作業環境の質」まで考える必要があります。
デスクワークの電力需要を過小評価するな
「パソコンとデスクライトがあれば十分でしょ」
そう思っていた私は、在宅ワーク開始2週間で現実を知りました。
実際に必要だったもの:
- ノートパソコン本体
- 外付けモニター×2台
- デスクライト
- スマホ充電器(仕事用)
- スマホ充電器(個人用)
- ワイヤレスイヤホン充電スタンド
- 外付けウェブカメラ
- 外付けマイク
- ルーター(仕事用)
- 外付けハードディスク
- タブレット充電器
11個。11口のコンセントが必要だったんです。
配線の「見た目」が集中力を左右する
もう一つ、実際に働いてみて気づいたことがあります。それは「配線の見た目が、集中力に影響する」ということ。
コードがデスクの上を這い回り、絡まり合っている状態。これは、視覚的なノイズです。無意識のうちに気が散り、集中力が削がれます。
逆に、コード類が完全に隠れて、デスク上がスッキリしている状態。これだけで、作業効率が明らかに上がるんです。
デスク背面配線システム
私が後から導入して大成功だった方法が、「デスク背面配線システム」。
デスクの背面に配線用のトレーを設置し、すべてのコード類をそこに収納。デスクの上には、必要最小限のケーブルだけが顔を出す仕組み。
コンセント自体は、床から10センチの低い位置に8口を横一列に配置。デスクで完全に隠れるので、正面からは一切見えません。
この配線システムのおかげで、デスク上は驚くほどスッキリ。仕事のモチベーションが上がり、作業効率も向上しました。
もし家を建てる段階に戻れるなら、壁内に配線用の空間を作り、完全に隠蔽できる構造にしたいくらいです。
リビングワークとプライベートの境界線
我が家では、私のワークスペースがリビングの一角にあります。
オープンで明るく、家族の気配も感じられて好きなのですが、一つ問題がありました。「仕事の機器」がリビングに常にある状態になり、オンオフの切り替えが難しいんです。
この問題を解決するために、カウンターデスクの下に引き出し式の収納を設置。仕事が終わったら、ノートパソコンや書類をすべてしまい、デスクの上を「何もない状態」にします。
充電は収納の中で行うため、収納内に4口のコンセント。外から見ると、ただのスッキリしたカウンター。でも引き出しを開ければ、完全な作業環境。
この「隠せるワークスペース」、リビングに仕事スペースを作る人には本当におすすめです。
「見せない電源設計」という美学
ここまで、様々な部屋のコンセント配置を見てきました。そして、一つの共通点があることに気づいたでしょうか。
それは「隠す」という発想です。
高級ホテルに学ぶコンセント美学
高級ホテルの部屋を思い浮かべてください。洗練されていて、美しくて、でも必要なものはすべて揃っている。
その秘密の一つが、「電源を見せない工夫」なんです。
コンセントは家具の背面や側面に配置し、コード類は配線モールで隠す。テレビ周りも、デスク周りも、ベッド周りも、コードが視界に入らないように徹底的に設計されています。
この「見せない美学」を、私たちの家にも取り入れることができます。
アクセントウォールとコンセントの色合わせ
寝室の一面を、深いグリーンのアクセントクロスにしました。落ち着いた、大人っぽい雰囲気。とても気に入っていました。
でも、引き渡しの日に気づいたんです。白いコンセントが、グリーンの壁で異様に目立つことに。
すぐに、ホームセンターでグレーのコンセントカバーを購入し、交換しました。たった1,000円程度の投資ですが、効果は絶大。違和感が完全に消え、壁と調和しました。
これ、建てる前に気づいていれば、最初からグレーのコンセントを発注できたのに…。
コンセントカバーという選択肢
最近は、おしゃれなコンセントカバーがたくさん売られています。
木目調、レザー調、真鍮製、アンティーク風、モダンデザイン…。インテリアに合わせて選べます。
「コンセントを隠す」のではなく、「コンセントを見せる」という逆転の発想。これも一つのアプローチです。
特に、カフェ風やインダストリアル風のインテリアを目指す人には、真鍮製のコンセントカバーがおすすめ。存在感がありながら、おしゃれで、むしろインテリアのアクセントになります。
エアコンコンセントの天井設置
リビングのエアコンのコンセント、実は天井に付けてもらいました。
通常は壁面に付けるのですが、天井に付けることで、エアコン本体の真上に配置。下から見上げてもほとんど見えず、コードも極端に短くなります。
追加費用は5,000円程度でしたが、見た目のスッキリ感は大きく違います。
特に、吹き抜けのあるリビングや、高い天井の部屋では、この天井設置コンセントが威力を発揮します。視線が上に向きやすい空間だからこそ、エアコン周りの美しさが重要なんです。
「失敗から学ぶ」後悔ポイント5選
ここまで、成功例を中心にお伝えしてきました。でも、正直に言えば、失敗もたくさんあります。
その失敗を、包み隠さずお伝えします。あなたが同じ失敗をしないように。
失敗1:ソファ裏のデッドコンセント
リビングのソファの配置を、しっかり計測せずに決めてしまいました。その結果、ソファの真後ろにコンセントが来てしまい、完全に隠れて使えない状態に。
3口のコンセントが、まるで「ないもの」に。建てる前に家具の正確なサイズを測り、図面に書き込んでいれば防げた失敗です。
失敗2:玄関の照明用コンセント忘れ
玄関に間接照明を置きたかったのに、コンセントを付け忘れました。
結果、延長コードを廊下から引っ張ってくる羽目に。来客時、床を這うコードが恥ずかしくて、間接照明を諦めました。
玄関は「必要ないだろう」と思いがちですが、実は照明やディフューザー、季節の飾り物の電源など、意外と必要になります。
失敗3:子ども部屋の偏った配置
娘の部屋のコンセントを、窓側の壁に集中させてしまいました。
当時は「机は窓際に置くもの」と思い込んでいたんです。でも、娘が小学校に上がると「窓の光が眩しい」という理由で、机を反対側の壁に移動したいと言い出しました。
でも、そちらの壁にはコンセントが1口しかない。結局、長い延長コードを引き回す羽目に。
壁面に分散して配置していれば、こんな問題は起きませんでした。
失敗4:ダイニングの床コンセント見送り
ダイニングテーブルの近くに、床埋め込み式のコンセントを提案されました。でも、「そこまで必要ないかな」と思い、見送りました。
今、毎週末、ホットプレートを使うたびに延長コードを引っ張り出しています。子どもが足を引っかけそうになることも何度か。
床コンセント、付けておけば良かったと本気で後悔しています。
失敗5:パントリーのコンセント数不足
パントリーに2口のコンセントを付けました。「収納だから、これで十分」と思っていました。
でも実際は、ホームベーカリー、ヨーグルトメーカー、ミキサー、コードレス掃除機の充電スタンド…。収納内で充電・使用したいものが次々と増えました。
今は2口を奪い合う状態。あと2口、いや4口欲しい。収納スペースこそ、「隠して使える」ので、多めにコンセントを付けるべきでした。
「迷ったら付ける」が正解である理由
これまでの話を聞いて、こう思ったかもしれません。
「でも、使わないコンセントがたくさんあるのも、もったいないんじゃ?」
確かに、そう感じるのは自然です。でも、経済的に計算すると、実は「付けておく」方が合理的なんです。
建てる前と後のコスト差
新築時にコンセントを1口追加するコスト:3,000〜5,000円
建築後にコンセントを追加する場合:
- 電気工事費:20,000〜30,000円
- 壁の開口・復旧:10,000〜20,000円
- 内装の補修:10,000〜15,000円
- 合計:40,000〜65,000円
なんと、10倍以上の差があります。
つまり、「使うかどうか分からない」コンセントでも、建てるときに付けておいた方が、経済的にも合理的なんです。
「余裕」が生む心理的安心感
もう一つ、数字では測れない価値があります。それは「余裕があることの安心感」。
「この部屋、コンセント足りるかな…」という不安を抱えながら暮らすより、「どこにでもコンセントがある」という安心感の中で暮らす方が、ずっと快適です。
新しい家電を買いたいとき、「コンセントがないから諦める」のではなく、「欲しいから買う」と素直に決められる。この自由さが、生活の質を高めます。
「将来の自分」への投資
家は、30年、40年、あるいはそれ以上住み続ける場所。
今は必要なくても、5年後、10年後に必要になるかもしれません。子どもが生まれる、親と同居する、在宅ワークが増える、趣味が変わる…。
人生には、予測できない変化がたくさんあります。
その変化に柔軟に対応できる家にするためには、「余裕のあるコンセント計画」が不可欠。それは、将来の自分への投資なんです。
設計士さんの「提案」は聞くべき
私が最も後悔しているのは、設計士さんの提案をいくつか断ってしまったこと。
「ここにもコンセントがあると便利ですよ」と言われたのに、「いや、大丈夫です」と断った場所が3箇所あります。
今、その3箇所全てで、「付けておけば良かった」と思っています。
設計士さんは、何十軒、何百軒もの家を設計してきたプロフェッショナル。その経験から「ここは必要になる」と分かっているんです。
だから、設計士さんが「あった方がいい」と提案してくれたら、素直に聞くべきです。少なくとも、「なぜ必要か」を詳しく聞いてから判断すべきでした。
まとめ:コンセント配置は「未来の暮らし」を設計すること
3年前、私はコンセント配置を「地味な作業」だと思っていました。壁紙や床材を選ぶような「楽しい家づくり」とは別の、事務的な作業。
でも今は違います。
コンセント配置は、「未来の暮らし」を具体的に設計する作業だったんです。
朝、どこで身支度をするか。夜、どこでくつろぐか。週末、家族とどう過ごすか。子どもが成長したら、どう暮らしが変わるか。
そうした「動詞」と「時間」を丁寧に想像し、形にしていく。それがコンセント配置なんです。
この記事で伝えた17の真実
- 現代生活は「充電依存型」であり、その認識からスタートする
- 電化製品は確実に増えるので、5年後を見据えて計画する
- 洗面所は朝の時間圧力を考慮し、家族人数+2口を基本に
- キッチンは「層」で考え、調理台・収納・パントリーに分散配置
- パントリー内のコンセントは「隠す収納」として活用価値が高い
- リビングはソファからの「3メートル圏内」に必要なものを配置
- 子ども用充電ステーションを作ると家族の平和が保たれる
- 寝室は「就寝前30分」の行動を想像し、枕元に5〜6口確保
- コンセントの高さは「ベッドに横になったまま届く」位置に
- 子ども部屋は10年後の成長を見据え、壁面分散配置で柔軟性を
- 在宅ワークスペースは1人あたり8〜11口、配線を隠す設計に
- 収納内コンセントは生活感のある機器を隠すのに最適
- アクセントクロスとコンセントの色を調和させる美学
- エアコンコンセントは天井付けで視覚的スッキリ感を実現
- 家具の実寸サイズを図面に書き込み、隠れるコンセントをゼロに
- 設計士さんの提案は経験に基づくので素直に聞くべき
- 迷ったら付ける、建築後は10倍以上のコストがかかる
新しい家での暮らしは、毎日が発見の連続。「ここにコンセントがあって良かった」と思う瞬間も、「ここに欲しかった」と後悔する瞬間も、どちらも訪れます。
でも、建てる前に時間をかけて考えることで、「良かった」の瞬間を圧倒的に増やすことができます。
あなたの新しい家が、毎日快適で、美しく、そして何より「あなたらしい暮らし」を実現する場所になりますように。
コンセント配置、ぜひ楽しみながら、そして真剣に向き合ってください。